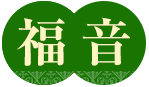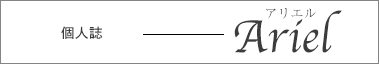- - 【説教】悲しむは幸いである ─ 尹東柱の詩「八福」と重ねて
- - 【説教】イエスの最初の弟子アンデレ
- - 【2026 尹東柱追悼式】
- - 【説教】イエスの洗礼
- - 【尹東柱と三木清】
- - 【説教】イエスの名の力と働き
- - 【説教者の祈り】
- - 【説教】わたしたちはその栄光を見た
- - 【説教】この子は自分の民を罪から救う
- - 【おはなし】星をうたう心で ─ 詩人 尹東柱の信仰と平和への思い
- - 【説教】来るべき方は、あなたでしょうか
- - 【説教】その上に主の霊がとどまる
- - 【説教】主はわたしの牧者
- - 【尹東柱 詩 対訳 11編】2025/12/13
- - 【案内】星をうたう心で ─ 詩人 尹東柱の信仰と平和への思い
- - 【説教】わたしを贖う者は生きておられる
- - 尹東柱「山間の水」
- - 【説教】悲しむ人々は
- - 【講演】張準相司祭・聖ガブリエル教会と大阪教区
- - 【説教】神様、罪人のわたしを憐れんでください
【説教】アンナという女預言者がいた
ルカによる福音書 2:22-40
2025年2月2日・被献日
上野聖ヨハネ教会にて
今日2月2日は被献日、幼子イエスが生まれて40日目に、神殿で神に献げられたことを記念する日です。
幼子イエスがマリヤとヨセフに抱かれてエルサレムの神殿に連れて来られたとき、そこで二人の老人に会いました。一人はシメオンというおじいさん、もう一人はアンナというおばあさんです。今日はアンナに目を留めてみることにしましょう。
「また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若いとき嫁いでから七年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、八十四歳になっていた。」ルカ2:36-37
名前はアンナ。84歳という高齢です。短い記述ですが具体的に彼女のことが記されています。イスラエルの12部族の中のアシェル族に属する。お父さんの名はファヌエル。彼女が歩んできた人生について、こう記されています。
「若いとき嫁いでから七年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ」た。
当時の女性は遅くとも10代の半ば過ぎには結婚したとされますので、夫と死に別れたのは20代の半ばにもならなかったと思われます。それからおよそ60年を生きてきました。
当時の男性中心の社会にあっては特に、夫を失った女性の立場は非常に弱いものでした。生活がたちまち切迫したでしょう。子どもがあったとすればその養育は大変だったでしょう。死ぬような辛い思いをすることが何度もあったかもしれません。そうした中で彼女はただ一つのものにすがりつきました。神さまです。神さまだけを頼りに生きてきたのです。
「彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。」2:37
「彼女は神殿を離れず」とあります。実際にエルサレム神殿の一角に暮らしたのか、それとも連日神殿に行って祈りを捧げたということか。それはともかく、夫が亡くなって以降アンナは、どんなことがあっても神さまから離れず、祈って祈って、神にすがって生きてきたのです。
アンナはそうした日々を重ねる中で、神の声を聞くようになりました。聖書の言葉が立ち上がって彼女に語りかけてくるのです。アンナは、自分に語りかけてこられる神の言葉を、苦しみや悲しみを抱えた人々に伝えました。それを聞いた人たちは、神からの慰めと励ましと導きを受けました。アンナをとおして神さまの声がはっきり聞こえる。それで彼女は、預言者と呼ばれるようになったのです。
「そのとき、近づいて来て神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。」2:38
アンナは今日も祈るために神殿に来ました。そしてそのとき、幼子イエスと出会いました。彼女にははっきりとわかった。この幼子が、聖書に約束された救い主、自分たちが待ち望んできた方であると。彼女の心は喜びに溢れました。神を賛美せずにはおれませんでした。そうして、神の救いを待ち望んでいるエルサレムの人々皆に、この幼子のことを話したのです。
ここで、このアンナのことから思い浮かぶ一人の女の人のことをお話ししたく思います。今からもう38年も前の1987年、わたしは聖公会神学院の教員をしていて、神学生たちと一緒に約2週間の韓国研修旅行に行きました。合わせて20数名だったでしょうか。ある日、ソウルから南へ3時間くらいのところにある小さな農村、堤岩(チェアム)というところを訪ねました。そこで一人の高齢の女性に出会いました。田同禮(チョンドンネ)さん。90歳近い方で、そこの堤岩教会の長老をされていました。
……
 RSS
RSS